2. 小学校の教員に~文字と関わる毎日の始まり~
前回のブログ【その1】の続きです。
美文字に興味があり、
〇どうやって美文字になれるのか知りたい方
〇お子さんに美文字を学ばせたいが、どんな教室・講座に通わせればよいか迷っている方
〇書道を習っているのに、普段の字はきれいに書けないと感じている方
〇幼稚園の先生や小学校の先生で、字を書くこと、字の書き方を教えることに苦手意識のある方
こんな方に向けて、「美文字への道」として、講師の経験談をお伝えしています。
【その1】はこちらをご覧ください。
今日は、続き【その2】になります。
2. 小学校の教員に~文字と関わる毎日の始まり~ です。

目次 「美文字への道」
1. まずは書道教室に。毛筆は書けても硬筆は・・・
2. 小学校の教員に~文字と関わる毎日の始まり~ 【その2⇒今回のブログ】
3. 小学校の現場で感じた「鉛筆の持ち方」の重要性
4. 書写との出会い
5. 教えることで美文字スキルアップ!
6. 回り道をした私だからお伝えできる美文字のこと
2. 小学校の教員に。文字と関わる毎日の始まり
大学を卒業後、念願の小学校教員になりました。
専門教科は国語ではなかったため、文字の指導については大学で軽く触れた程度でしたが、書道経験があったため、それなりに字を書くことはできました。しかし、美しく整った文字とは言えず、いつも美文字への憧れが心の中にありました。
当然ですが、教員(特に小学校)というのは「書くこと」「話すこと」の比重が非常に高い仕事です。
「書くこと」でいうと、
・国語や書写指導(ひらがな、漢字指導など)
・板書
・宿題のノートチェック(書き取りノートの丸付け、直し。音読カードなどへのコメント記入など)
・コンクールや行事などの際に渡す賞状への名前書き(筆ペン)
・通信票の所見欄を書く
・保護者からの連絡帳にお返事
・子どもの作品やノートへの朱書きコメント
など、毎日の指導の中で、手書きの場面は想像以上に多かったのです。
今でこそ、通信票の所見はパソコンが当たり前ですし、賞状や掲示物の名前もパソコンで印刷できたり、電子黒板が登場したりと、手書きでなくても対応できる場面は増えているのですが、ひと昔前まではこのような状況でした。
最初は黒板に字を書くだけで緊張しました。子どもたちがジッと集中して見ている前で字を書くのです。書き順や誤字脱字などの間違いがないか、気を遣いました。チョークの扱い方もコツをつかむまでは時間がかかりました。
このような生活の中で、もっともっと字をきれいに書けるようになりたい、という思いがまた沸き上がってきました。
そして再び書道を習いたい。そう思い、日展入選経験のある先生に書道を教えていただくことにしました。
ところが、書道自体は楽しかったものの、古典の臨書を中心に教わることが多かったため、自分はそれを日々の文字に生かすことができませんでした。
数年間学び、師範の免状をいただきました。書道の技術は上がりましたが、「ひらがな」や「漢字」など、日常の文字はあまり変わりませんでした。
そして、まだ美文字(硬筆)へのモヤモヤとした思いはなくならないままだったのです。
















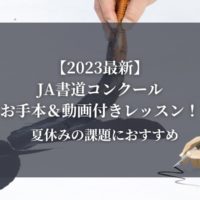


この記事へのコメントはありません。